| スレスフルな社会生活に果敢に立ち向かっている現代人は誰もがメゲたり、凹んだりします。その理由もメカニズムもさまざまです。 「エゴ・レジリエンス」とは、日々のストレスをうまく調整して元気な自分を維持する力、誰もが持っているパーソナリティの弾力的な力です。「エゴ・レジリエンス」を高めることで自我のバランスをとる力が強化され、メゲても凹んでも、すぐに立ち直ることができるのです。 エゴレジ研究所の小野寺と畑が、「エゴ・レジリエンス」関連のお役立ち情報を提供し、あなたの元気をサポートします。 |
食事は私たちの毎日の生活に欠かせないもの。1日3食で年間1095食を口にしていますが、これらが心の豊かさにどれだけ直結しているのでしょうか。食べることでほっと一息ついたり、活力になったり、コミュニケーションのきっかけになるなど、人それぞれさまざまな生活の一部になっているかと思います。そこで今回は、食べることの心理的影響についてのお話です。

食べることの心理学
食べることは、感情や行動、記憶、社会的なつながりに大きな影響を与えます。心の状態によって、食への意識が変化します。多くの研究から以下にかいつまんであげてみます。
1.感情と食欲の関係
ストレスと食事:ストレスを感じると、コルチゾールというホルモンが分泌され、食欲が増加します。多くの場合、炭水化物や脂肪分の多い「快適な食べ物」を求める傾向があり、これらを摂取することで、ドーパミンが分泌され、一時的な幸福感が得られるためです。
感情を補完する食行動:悲しみや孤独を感じると、人は甘いものや高カロリーの食品に手を伸ばす傾向があります。
2.食事の記憶と心理の影響
幼少期の経験:子供の経験は、やがて親や家族と一緒に食べた料理の味や香りを深く記憶に残します。安心感や懐かしさをもたらし、大人になってからの食の嗜好にも影響を与えます。
ノスタルジックな食体験:特定の料理や香りは、過去の幸せな記憶を呼び起こします。これが「味わった心の安定感」の期待の一つです。
3.社会的な役割と食の心理
食事による絆:一緒に何かを形成することは、人間関係を深める重要な行動です。食卓での会話や共通の食体験は、家族や友人、同僚との絆を強化します。
孤食と心の健康:一人で食べる「孤食」は、寂しさや孤独感を加速する恐れがあります。ですが、意識的に楽しむ「ソログルメ」など、ポジティブな孤食文化も注目され、これらはストレス発散にもなります。
4.食事行動と自己表現
食の選択と認識:ヴィーガンやベジタリアン、地産地消を重視する選択など、食べるものの選択は自己の価値観やライフスタイルを表現する手段となります。
特定の食事の好み:「甘党」「辛党」など、食の好みは個人の性格や心理状態と関連しています。
5.満腹感と心理的満足
物理的満腹 vs. 心理的満足:夕食後に「まだ何か食べたい」と感じるのは、心理的な満足感が得られていない状態です。
食べるスピードと満足感:早く食べると満腹感が得られにくく、このため、マインドフルイーティング(食事を意識的に味わう行為)が注目されています。
6.食と文化の心理的影響
伝統料理の心理的効果:伝統的な料理や郷土料理は、文化的認識を強化し、自分が所属するコミュニティへの帰属意識を高めます。
異文化の食事体験:異なる文化の料理を楽しむことは、新しい視点や刺激を与え、自分の世界観を広げるきっかけに繋がります。
7.食べる行動の心理的課題
感情的な過食:不安やストレスにより、必要以上に食べてしまう「感情的過食」は、肥満や健康問題につながるだけでなく、自己嫌悪に陥る可能性があります。
摂食障害:心理的課題(自己評価の低さ、完璧主義など)が原因で、過食症や拒否食症といった摂食障害に。これらは食べる行動と心理の健康の重要性の関連を示しています。

感情が食事に与える影響と食事が感情に与える影響
感情は私たちの食事行動に大きな影響を与えます。喜び、悲しみ、ストレスなど、様々な感情が食欲や食事の選択に関わっています。
◆ネガティブな感情と食事行動
ネガティブな感情は、多くの場合、不健康な食事行動につながる傾向があります。例えば、ストレスや悲しみを感じているときに、高カロリーの食べ物や甘いものを過剰に摂取してしまうことがあります。これは、食べることで一時的に気分が良くなるためです。
◆ポジティブな感情と食事行動
一方で、ポジティブな感情は、健康的な食事選択につながる可能性があります。幸せな気分のときは、より栄養バランスの取れた食事を選ぶ傾向があります。また、食事を楽しむことで、さらにポジティブな感情が強化されることもあります。
◆感情と食事量の関係
感情の状態は、食事の量にも影響を与えます。ストレスを感じているときは、過食や拒食といった極端な食事行動につながる可能性があります。感情のコントロールが難しい状況では、食事のコントロールも困難になることがあります。
◆栄養と感情の関係
特定の栄養素は、脳内の神経伝達物質の生成に関与し、私たちの気分や感情に直接的な影響を与えます。例えば、トリプトファンを含む食品は、セロトニンの生成を促進し、気分を向上させる効果があります。
◆食事のタイミングと感情
食事のタイミングも感情に影響を与えます。朝食を摂取することで、認知機能が向上し、ポジティブな感情が増加することが示されています。一方で、不規則な食事パターンは、感情の不安定さにつながる可能性があります。
◆食事の質と感情の変化
食事の質も重要な要素です。バランスの取れた健康的な食事は、長期的に見てメンタルヘルスの向上につながります。反対に、過度の糖分や脂肪の摂取は、短期的には快感をもたらすものの、長期的には気分の落ち込みやうつ症状のリスクを高める可能性があります。

食べることの2度の幸せ
おいしいものを食べているとき、私たちはこの上ない「幸せ」を感じます。その際に脳から放出されるのが神経伝達物質であるドーパミン。この「幸せホルモン」としても知られるドーパミンが、おいしい食事によって脳から「2度」放出されていることがドイツのマックスプランク研究所が行なった研究で明らかになりました。
※https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1550413118307435?via%3Dihub
新たに開発されたポジトロン断層法(PET検査)により、ドーパミンが多く放出されるタイミングや、それに関わる脳のエリアを特定することもできるようになりました。そして分析の結果、最初のドーパミン放出が脳の報酬や知覚と関わる領域で起こっていたのに対し、2度目の放出については、そうした領域に加えてより高次な認知機能に関わるエリアも関与していることが分かりました。
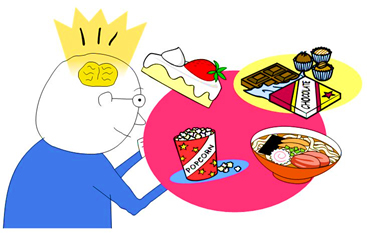
ドーパミンが放出される2度のタイミングは、1つ目は「口に入れたとき」、そして2つ目は「食べ物が胃に到達したとき」です。
実験では、12人の健康なボランティアがPET検査で記録をしながら「おいしいミルクセーキ」か「味のない液体」のどちらかを口にしました。その結果、興味深いことに被験者の「ミルクセーキが飲みたい」といった欲望のレベルが高ければ高いほど、はじめに放出されるドーパミンの量が多く、2度目のドーパミンの放出が少ないことが明らかとなりました。
「胃」によってもたらされる2度目のドーパミンが抑制されることは、強く「食べたい」と思ったものを食べ過ぎてしまうといった現象につながってしまいます。人は十分な量のドーパミンが放出されるまで、食べることを止められないのです。つまり、おいしいものをついつい食べ過ぎてしまうのは、2度目のドーパミンが不足しているからなのかもしれません。「口」ではおいしい食べ物も、「胃」はあまり幸せにしてくれないことが分かったこの研究。研究を率いたHeiko Backes氏は、この仮説にはさらなる研究が必要であるとしていますが、研究が進めば「食べ過ぎ」を防ぐための画期的な方法が編み出される可能性もあります。

以上、エゴレジ研究所から食べることの心理的影響についてご紹介しました。人間が本来「食べたい!」という欲求は、体のエネルギー不足からです。ですので、自分の体に取り入れたい要素を欲します。その食べたい時に、一番欲するものを、直感で感じます。その時の体の状態によって、ビタミン・ミネラルを多く欲したり、マグネシウムだったりするのです。そんな風に直感で欲する食べ物は、まさに体が必要としている食べ物と一致します。
エゴレジ研究所は,生涯発達心理学,パーソナリティ心理学,ポジティブ心理学の領域からの調査研究の成果を活かし,「エゴ・レジリエンス」をキー・コンセプトとして,いきいきと人生を楽しむことができる社会の実現に貢献することを目指しています。
あなたの元気のアドバイザー「エゴレジ研究所」
https://egoresilabo.com/

<プロフィール>
 |
代表 小野寺敦子/ 心理学博士
目白大学 人間学部心理カウンセリング学科教授
|
|
|
GM 畑 潮/心理学博士 GCDFキャリアカウンセラー 健康リズムカウンセラー |


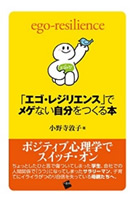









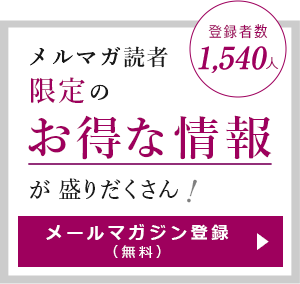

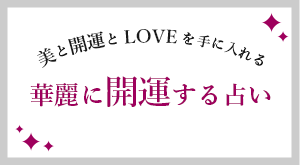
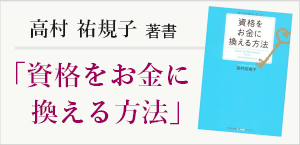
この記事へのコメントはありません。