| スレスフルな社会生活に果敢に立ち向かっている現代人は誰もがメゲたり、凹んだりします。その理由もメカニズムもさまざまです。 「エゴ・レジリエンス」とは、日々のストレスをうまく調整して元気な自分を維持する力、誰もが持っているパーソナリティの弾力的な力です。「エゴ・レジリエンス」を高めることで自我のバランスをとる力が強化され、メゲても凹んでも、すぐに立ち直ることができるのです。 エゴレジ研究所の小野寺と畑が、「エゴ・レジリエンス」関連のお役立ち情報を提供し、あなたの元気をサポートします。 |
時代劇は単なる娯楽ではありません。心を癒す遊び場を提供してくれます。アクション、ユーモア、そして道徳的な明快さが融合した時代劇は、他に類を見ないほど爽快なメンタルケアを提供してくれます。そこで今回は、時代劇のメンタル効果についてのお話です。

痛快娯楽時代劇の効用
1. 頭を空っぽにするエスケープ効果
時代劇の痛快な展開やほっこりする人情話に身を任せることで、仕事や人間関係のストレス、社会的不安などから一旦解放され、雑念を払いのけられます。
2. 明快な善悪観が心の安定をもたらす
勧善懲悪の物語は「悪を裁き、善が報われる」構図を提示することで、内面的な葛藤や判断迷いを和らげます。複雑な現実を一瞬忘れ、明確な正義感に癒されることで、心に静かな安定が生まれます。
3. カタルシスでストレスを解放
悪役に対する主人公の逆襲や裁きの場面は、観る側の怒りやフラストレーションを代替的に発散させてくれます。一連の痛快なアクションや復讐譚を目撃することで、体内の緊張が一気に解け、深い爽快感と安心感が得られます。
4. 知恵と気概を味わう自己効力感の向上
理不尽な悪計で苦境に立たされながらも機知や信念で困難を乗り越える主人公の姿は、観る側にも「困難は乗り越えられるかもしれない」という前向きな自己感覚を刺激します。

5. 共感によるつながり感の回復
登場人物同士の助け合いや情に厚いエピソードは、家族や友人など周りの人たちとの対話を誘発します。人情話に心を動かされて涙したり笑ったりする体験を共有する(共感する)ことで、孤立感が薄れ、人間関係の温かさを再認識できます。
6. ノスタルジアと安心感の演出
時代劇や昔話特有の情景描写、古き良き人情を感じさせるエピソードは、現代の多忙さや情報過多から一歩引いた“ほっとする時間”を提供します。懐かしい調度や言い回しに包まれることで、心に潤いと安らぎが生まれます。
時代劇は、エスケープ効果、自己効力感の向上、感情のカタルシス、そして社会的つながりの再生を通じて、忙しい現代人の心に潤いを与える最適なメンタルケアツールだと言えます。
時代劇の名セリフ
時代劇の名セリフは、物語を通じて私たちの感情や人生観に強く働きかける力があります。その言葉を借りてストレスを和らげたり、自分を励ましたりすることで、心のケアに大きな効果をもたらします。
1. 感情の共鳴とカタルシス
✔ セリフに込められた切実な想いが自分の内面の悩みや葛藤と重なり合う
✔ 感情を言葉として外に出すことで、ストレスホルモンが減少し心が軽くなる
✔ 「泣いたり、怒ったり、笑ったり」というカタルシスの体験が、心のリセットを促す
2. 勇気や覚悟の醸成
✔ 主人公が不利な状況に立ち向かう言葉は、自分を奮い立たせるエネルギー源に
✔ セリフに込められた「生きる覚悟」「守るべきものへの忠義」といった普遍的テーマが、自己肯定感を高める
✓ 小さな一歩でもいいというメッセージが、不安や迷いを吹き飛ばしてくれる
3. 人生観の再構築
✔ 身命を賭して・・・など「一生一度の身の振り方」を問うセリフが、自分の選択を見つめ直すきっかけに
✓ 時代背景を超えて響く普遍的な価値観が、現代に疲れた心に安定感を与える
✓ ヒーローや侠客の生きざまから、自分らしい生き方のヒントを得られる
4. 文化的アイデンティティの強化
✔ 日本の歴史や伝統に根差した言葉を享受することで、郷愁や帰属意識が深まる
✓ 日常会話でそのセリフを引用するだけで通じ合える仲間意識が孤独感を和らげる
✓ 文化的背景を理解しながら自分のルーツを再確認できる
また、時代劇の名セリフを実際に口にすると、単なる鑑賞とは違うレベルで心と体に作用します。これは演劇や朗読の効果と似ていますが、時代劇特有のリズムや言葉の力が加わることで、より深い心理的・身体的な変化が期待できます。
大人女子と時代劇
真田広之の「将軍」が世界で評価され、「侍タイムスリッパー」が話題で、改めてその価値が見直されている日本の時代劇。
時代劇は歴史や人情だけじゃなく、大人女子ならではの視点で楽しめる“いいこと”がたくさんあります。
例えば――
● 着物や所作の美しさから学べる所作術
● 強くしなやかな女性像に触れて、自分の生き方のヒントを得られる
● 恋愛や友情、家族愛など、普遍的なテーマを深く味わえる

好調の時代劇専門チャンネルで企画・プロデューサーとしてらつ腕をふるう日本映画放送株式会社・宮川朋之編成制作局長によれば、
“時代小説では池波正太郎、藤沢周平、司馬遼太郎などがエグゼクティブに人気ですね。とりわけ池波、藤沢作品では必ずといっていいほど、武家、庶民、果ては盗賊までそれぞれの世界の住人たちの「葛藤」が描かれていて、特徴となっています。エグゼクティブの皆さんも、小説に出てくる主人公の心の葛藤を、自らのビジネスでの境遇に重ね合わせているのかもしれません。現実は、勧善懲悪型の物語のようにシンプルにはいかないですから。その意味で、われわれも新しい時代劇ではこの「葛藤」を丁寧に描くよう心がけています。
・・・
それからもうひとつ、時代劇には「覚悟」という要素がありますね。今はなにもかもが自由で、自由の価値がわからなくなっている時代といえます。しかし、江戸時代はそうではなかった。職業の自由も、恋愛の自由もない。生まれ落ちた瞬間から、それぞれが運命を覚悟して生きなければならなかったんですね。
刀のツバがありますよね。武士のなかではトンボをかたどったツバが人気だったそうです。理由がとっても面白いんですよ。刀を抜くとき、もっとも「覚悟」が必要だった武士たちは、まっすぐにしか飛ばないトンボの生き様にあやかりたかったようです。一度、刀を抜いたら後にはひけない。そのとき、一瞬で判断をし、覚悟を決める。時代劇はそういうことを題材にしたドラマなんです。この点でも、なぜエグゼクティブが時代劇を好むのか、理解できる気がします。
・・・
時代劇で四季を描くとき、象徴となるのが食事のシーンです。これをどう表現するかで世界観が変わってくる。たとえば春の旬の野菜を食べて、ただ「おいしいね」と言わせてはダメで、「この苦味がたまらんな」と言わせるんです。これを理解するというのはひとつの教養ですよね。考えてみたら先に挙げた池波正太郎らも健啖家で、小説作品のなかでその知識が活かされている。宴席での会話などビジネスにも活かせる知識として、「食文化」は案外、大事なキーワードかもしれません“。

以上、エゴレジ研究所から時代劇のメンタル効果についてご紹介しました。時代劇は、単なる娯楽以上に心にじんわり効く“メンタル栄養”のような役割を果たすことがあります。静かな所作に宿る強さ、言葉の裏に潜む情、そして自分を見つめ直す時間——名作から新作まで、まだ出会っていない時代劇を発見したいものです。現実のモヤモヤに疲れたとき、心に響く時代劇の世界へエスケープしてみるのも一計かも。
エゴレジ研究所は,生涯発達心理学,パーソナリティ心理学,ポジティブ心理学の領域からの調査研究の成果を活かし,「エゴ・レジリエンス」をキー・コンセプトとして,いきいきと人生を楽しむことができる社会の実現に貢献することを目指しています。
あなたの元気のアドバイザー「エゴレジ研究所」
https://egoresilabo.com/

<プロフィール>
 |
代表 小野寺敦子/ 心理学博士
目白大学 人間学部心理カウンセリング学科教授
|
|
|
GM 畑 潮/心理学博士 GCDFキャリアカウンセラー 健康リズムカウンセラー |


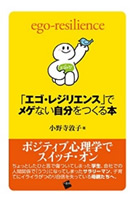




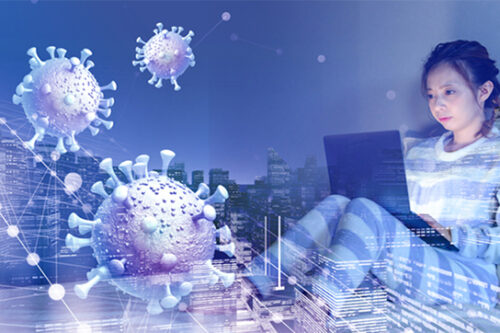

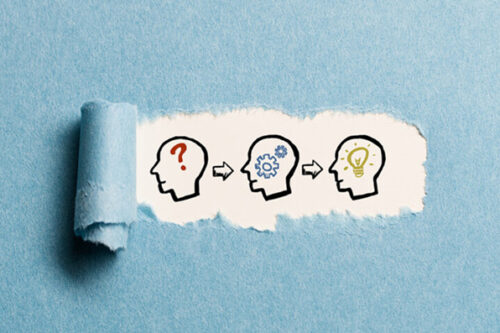


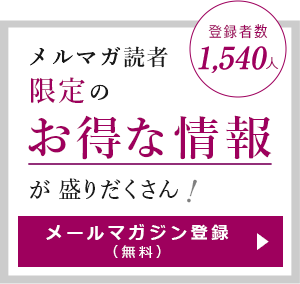

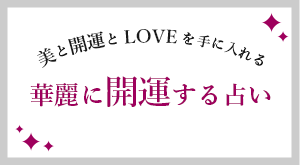
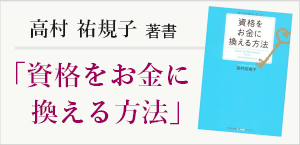
この記事へのコメントはありません。