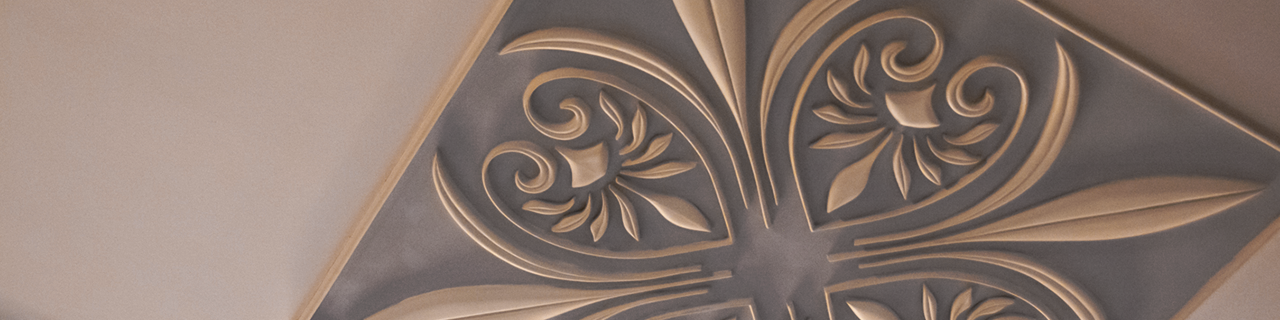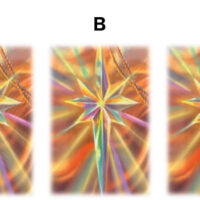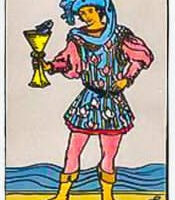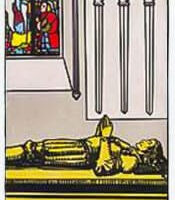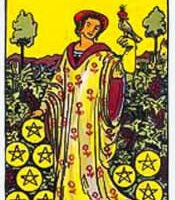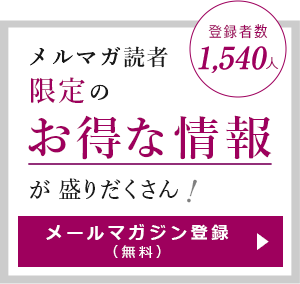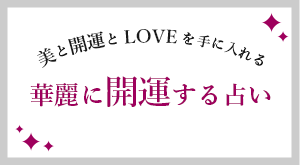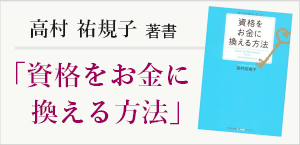こんにちは。女性ホルモンに着目した国産オーガニックスキンケア・ブランド創始者の宮武です。
神楽坂女子メンバーの中には、「カラダに関わるお仕事」をしている方も多いのではないでしょうか?
またご自身の体調の変化や介護などを機に、「カラダ」について関心が高まっている方もおられるかもしれませんね。
先日、ハワイで「人体解剖」を行ってきました。自分でメスをもち、ご献体を体内奥深くまで解剖を行うものです。
もちろんただの興味本位で行うものではありません。カラダに関わるお仕事は、お客様の体に皮膚の上からアプローチして皮膚の下に影響を及ぼすのですが、実際には皮膚の下を見たことがない。
ところがハワイではアロマセラピストのようなお仕事も「医療従事者」の一部として扱っていただけることから、「人体解剖」という医療行為をさせていただき、「皮膚の下」を直接確認させていただくことができる。
そんなわけで大変貴重な機会をいただきましたので、みなさんにも少しその様子をシェアさせていただきますね!
※血みどろの怖い話は出てきませんのでご安心ください。

1)皮膚の下は教科書とは全然違う
あなたは「全身の筋肉の図」とか「全身の骨の図」を見たことはありますか?
カラダに関わるお仕事でない方でも、学生時代、一度は目にしていると思います。
また「皮膚の構造はこうなっていますよ」「内臓はこうなっていますよ」などの図で私達は体内の状態を把握しているのですが、、、
実は、実際の体内の状態は全然違います。
実は私は人体解剖を3回行っているのですが、初めて人体解剖を行った時は、あまりの違いに面食らってしまい、なにがなんだかわからず終わってしまったのです。そのため最終的に計3回も人体解剖を行うことになったのですが、それぐらい、教科書で見ている情報と実際の体内は違いました。
たとえば、皮膚の厚さが全然違います。教科書では「表皮0.2mm、真皮2.0mm、その下に皮下脂肪」と学びますが、私が最初に解剖したご献体は、その10倍ぐらいありました。結論からいうと、ご献体が体の大きなハワイアンだったことや真皮と皮下脂肪の間に教科書では話題にもならない線維性隔壁が分厚くあったことなどが原因なのですが、でもその線維性隔壁はどんなやせ型の方にもあり、なぜ教科書ではこの部分を割愛されてしまっているのか、不思議に思うほどでした。
ただこれは教科書が悪いわけではありません。人間の体内は本当に千差万別で、しかも、各細胞の違いがわかりにくい。たとえば教科書では「動脈」「静脈」「神経」などがきれいに色分けされていますが、実際にはぱっと見はどれも同じに見えるので、毎日解剖を行っている医学部の研究者ですら「これはなんですか?」と聞かれて即答できるものではありません。その様子を見ていると、医療現場で医療ミスがめったに起こらないのが「神業」としか思えないほどでした。
また教科書では「脂肪」「筋肉」とキレイにわかれていますが、実際には筋肉の間に脂肪が入り込んだり、、、と霜降り状態のようになっていることも多く、この複雑な状態をよく教科書では簡潔にまとめたな、と感心するほどです。
そう考えると、あれだけ複雑な体内を簡潔にまとめてくれて、なかなか見ることができない体内を周知できるようにしてくれた先人たちの努力に感謝したくなりますが、とはいえ「教科書の状態がすべてではない」ことを理解しておかないと大変なことになるな、というのが私の実感でした。

2)どう生きるか? 生き方で体内の細胞はこんなに変わる
人体解剖のためのご献体は、病死した高齢者がほとんどです。それは献体になるためにはご本人とご家族の「今後の人類のために役立ててほしい」という意思表示が必要なためです。そのため、同じ「献体」とはいえ、そこにはその方の人生が詰まっています。
たとえば煙草を吸っていて肺がんで亡くなった方の場合。
肺は通常、20cm程度の大きな美しい器官なのですが、左側が肺がんになった方は5cmあるかないかの小さな黒い塊のような、残された右側とは同じものと思えない状態になっていました。
また脂肪も本来、キレイなミツロウのような色(はちみつ色)をしているのですが、不健康になるとこれがくすんだ、どす黒い色になります。

2回目の解剖のご献体は、とても印象的でした。
前立腺がんでなくなった79歳の男性だったのですが、おどろくほど体内が美しかったのです。まるで美術館に彫刻として飾ってあっても違和感がないほどの美しさでした。
人体解剖では故人の特定を防ぐために詳細な情報は与えられないのであくまで推測の範囲ではありますが、関係者で推測されたのは、この男性はおそらくがん告知されても治療をしなかったのでは、という見解でした。
アメリカでは医療費が大変高いため、病気になっても治療しない方もおられます。
いつかはなくなる天命だから、治療で延命せず、与えられた天命を存分に楽しもう、という考え方ですね。人それぞれいろんな考え方があってよいと思います。
おそらくこの男性は、そうなのではないか、と。
79歳で病死しているにもかかわらず筋肉は隆々、おそらく死の直前までサーフィンを楽しんだり、畑仕事をしたりしていたんだろうね、と想像ができました。
筋肉がその状態なので、脂肪も、ほかの細胞も、本当に美しい。
こんな美しい状態が私の体内にもあるのか、と思うと、自分に人間の体が与えられていることに誇らしく思うほどの美しさでした。

一方、中には全身の細胞がくすんでしまっている方もおられます。
細胞ひとつひとつに、その方の考え方や生き方が現れます。
今現在の私たちの考え方や生き方が体内の細胞1つ1つにこんなに大きな影響を与えているのか、と思うと、大切に生きたくなりますよね。

3)おそろしくて大切な、脂肪の話
あなたは「最近太ってきたな~」「痩せにくくなったな~」と感じたことはありませんか?年齢とともにそうなりますよね。うっかりするとネットから流れてくる「脂肪をとって痩せる!」的な広告が魅力的に見えてしまったりします。
が。
人体解剖を行うと、脂肪をとるのがいかに大変か、というのを痛感します。
私たちの体の脂肪は、筋肉が外界の刺激を直接受けないために、クッションの役割を果たすよう包んでいます。私たちは脂肪を嫌がりますが、実は脂肪は私たちを守ってくれる、「かなりいい奴」です。
とはいえ、増えすぎる(※)と減らしたいな~、と思いますよね。
※実際には脂肪の数が増えるのではなく、1つ1つが膨張して大きくなるだけです。
で「脂肪を取ろう!」という案が出てくるわけですが、、、
脂肪はそう簡単に取れません。
巷では若かりし日に「お腹の脂肪を胸に持ち上げて・・・」などというバストアップ法がありましたが、脂肪は皮膚の上から触ったぐらいでは移動しません。体内を解剖して直接脂肪を手で触っても動かすことはできません。移動させようと思うと、メスで周りの細胞と切り離さないとできません。私たちはなんとなくビーズクッションのようなイメージでいますが、実際には周りの細胞とがっちり結びついていて、メスで直接はがすのも一苦労、です。
しかも脂肪は数は増えないのですが、1つ1つが変幻自在に、どこまでも膨張します。そうなってくると、もう大変! 皮膚が伸びる限り、どんどん太ってしまいます。。。
解剖したメンバーたちで交わした言葉は「脂肪を減らすのは大変だね。つけないのが一番だね」でした。

とはいえ、脂肪は私たちの体にとって大変大切な存在です。3回目に解剖した方は糖尿病末期の方でした。糖尿病では食べ物の栄養をエネルギーに変えることができなくなるため脂肪を燃焼してエネルギーとして生きます。そのため、どんどん痩せてしまう。実際その方は脂肪がほとんどなく、日ごろから解剖を行っている先生ですら「こんなに少ないのは珍しい」と言われるほどでした。それを見ると、やっぱりある程度は脂肪を蓄えておきたいな~、と思うのでした。

いかがでしたでしょうか?
「人体解剖」は多くの人が体験できることではないので、貴重な経験としてみなさんとシェアさせていただきました。あなたがご自身の健康や生き方を考える上でなにかのきっかけになれば嬉しいです。
「カラダに関するお仕事をしている方」向けや「人体についての理解を深めたい方」向けには、10/1~10/3に3夜連続で「人体解剖シェア会」をzoomで行います。
ご興味のある方であればどなたでもご参加いただけますので、ご希望の方はこちらをチェックしてみてくださいね!アーカイブ配信は10月末日までです。
↓
https://www.jolve.jp/SHOP/G0007.html

またストレスから解放され、清々しく人生を送りたい方は、今週末の山中湖でのアウトドアSPAへぜひどうぞ!宿泊ご希望の方にはお得なご提案も可能です。ぜひお気軽にご相談くださいね!
↓
https://www.jolve.jp/hpgen/HPB/entries/60.html

リラックス、アンチエイジング、健康の話を3回にわたってお届けさせていただきました。あなたの人生になにか役立つことがあれば、とても嬉しいです。
最後までご覧いただき、どうもありがとうございました!

プロフィール
 |
宮武直子 株式会社ドルフィンズ代表取締役 女性ホルモンに着目した国産オーガニックスキンケア『jolve organic』開発者。「世界に伝えたい日本のエステティシャン20」選出アロマセラピストとして高級ホテル内に『jolve SPA』を運営、セラピスト養成機関『Globalセラピスト学院』学院長も勤める。大の自然好きが高じて、2017年、山中湖に移住。現在3拠点生活を送る世界一周アロマセラピスト。 |